俳句に親しんでみようとすれば、俳句という世界に入っていくわけですから、おのずと俳句とはどんなものか、
そのイメージがまずは自分の中にでき、そして親し むにつれて、季語などの約束事や表現の原則みたいなものが
次第に身につくものです。
文芸にそんなルールみたいなものは必要ないと考える方もあるかもしれません。
しかし、ルールと言っても法律のようなものではなく、良い俳句に共通する原則と考えたらいいかと思います。
ハマブン句会の投句者がそんな原則を知る手助けになればと思い、
テーマをピックアップしてお話ししたいと考えています。
| 題1回 |
| 説明をしない |
| 題2回 |
| 歴史的仮名遣いと現代仮名遣い |
| 題3回 |
| 切れ字のあり方 |
| 題4回 |
| 同じ意味、連想させる言葉をつかうな |
| 題5回 |
| 五七五は一個の詩である |
| 題6回 |
| 季語と季節感季節感 |
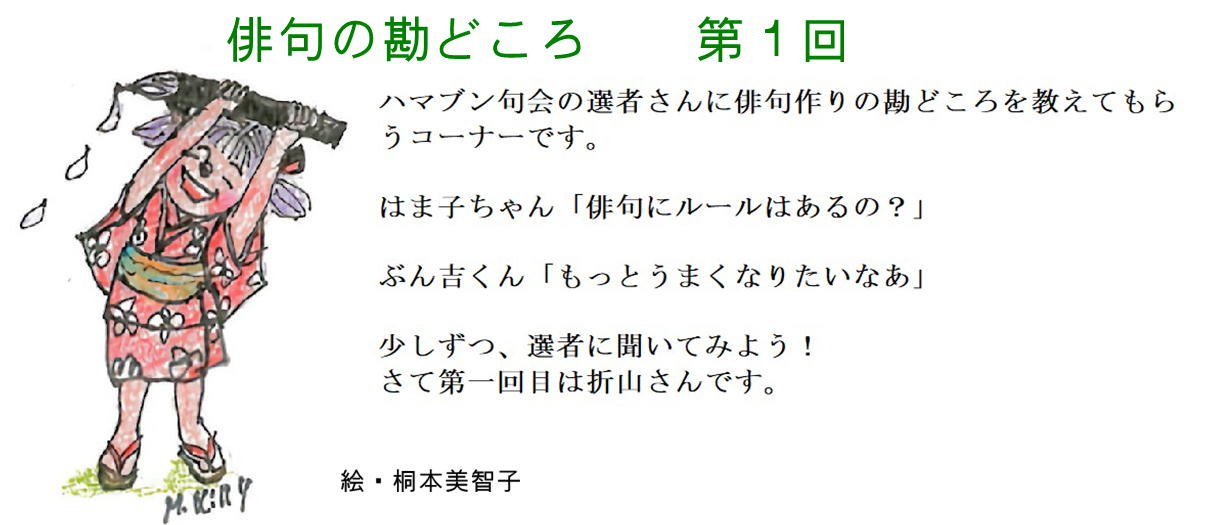
第1回.説明をしない
俳句は五七五、十七音の詩です。散文とも短歌とも違う性質を持っています。十七音しかありませんから多くを語れません。
説明したらとても 十七音では足りません。十七音で作者は一つの景色を提示します。
自然のありさまや人間の営みなどが提示されます。そこに作者の気持ちが込められます。
從って、悲しい、嬉しい、美しい、がさつだ、などの表現はしません。景色の中で解かってもらうということです。
また二重になる表現は避けるべきです。
投句の中からその点を改善すべきかなと言う句をあげてみますと
ブロックを握りて這い這いしてをりぬこの句はあかちゃんの状況を説明しています。
どこで説明を感じるかと言うと、「握りて」の「て」と「這い這いして」の「て」、そして「をりぬ」です。
「握っている状況ですよ」「這い這いしている状況ですよ」と言っています。
こう言われると「そうですか」と反応したくなります。でも微笑ましいです。景色はいいですね。
少し替えてみると整います。一つの例ですが
ブロックを握り這い這い春隣季語がなかったので春隣としました。
これで赤ちゃんの状況はよくわかるし季節感も出てくると思います
(折山正武)
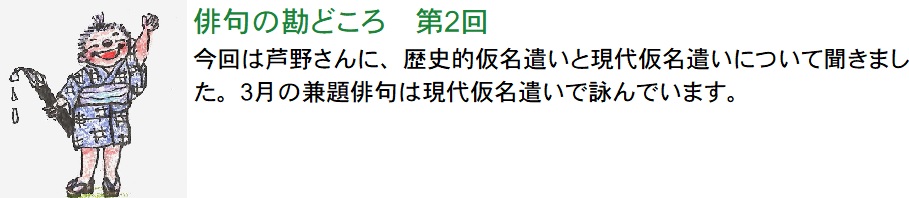
俳句の選者の指摘の中でよく見かけられるのが、仮名遣いの問題。
歴史的仮名遣いに時々現代仮名遣いが混じってしまうことだ。『旧かなづかひで書く日本語』(萩野貞樹著・幻冬舎新書)によれば、
[ハ行動詞](例:云ふ、給ふ、数ふ、合ふ等)と[ゐる]を使えれば、八割がたはカバーできるという。
●第一に覚えるのは、ハ行四段活用(云ふの例) 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形 いは いひ いふ いふ いへ いへ
●第二に覚えるのは、現代仮名遣いで下一段活用の動詞は歴史的仮名遣いで下二段活用となること(数ふの例) 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形 現代 数え 数え 数える 数える 数えれ 数えろ 歴史 数へ 数へ 数ふ 数ふる 数ふれ 数へよ
●第三に覚えるのは「ゐる」のワ行上一段活用(居るの例) 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形 ゐ ゐ ゐる ゐる ゐれ ゐよ
もちろん他にもたくさんあるので、覚えるのは大変。
筆者はまず声に出してみて、こんな感じだったかなと考えてから電子辞書で確かめている。
さて、それではなぜこんな思いをしても俳句は歴史的仮名遣いが主流なのかと問われれば、
現代仮名遣いより簡潔で美しいからだと筆者は思っている。現代仮名遣いは戦後の産物であり歴史が浅い。
それに比べて歴史的仮名遣いで書かれた歴史は圧倒的に深く、書きことばとして洗練されている。
3月の選者の句として現代仮名遣いの句を出させていただいた。
その第二句「あゝのどか錆びた自転車通る音」は、もともと「のどけしや錆びし自転車通る音」だった。
ただしこの句には文法的誤りがある。「錆びし」が間違い。「錆びる」の歴史的仮名遣いは「錆ぶ」。
「錆ぶ」の連体形は「錆ぶる」。しかしこの語はあまりに古い。それでいっそ現代仮名遣いにしてみようと思った次第。
しかし、上五の「のどけしや」も変えなければならないとなった時、はたと困った。
「のどかだな」。これでは小学生の句になる。それで「あゝのどか」としたわけだが「のどけしや」の言葉としての美しさに比べたら
分が悪い。切れも悪い。 筆
者自身は初めて現代仮名遣いで作句してみて少し面白かった。
歴史的仮名遣いではできるのに現代仮名遣いではできないというギャップ。
当分、現代仮名遣いでの作句も楽しみたいと思う。
(芦野信司)
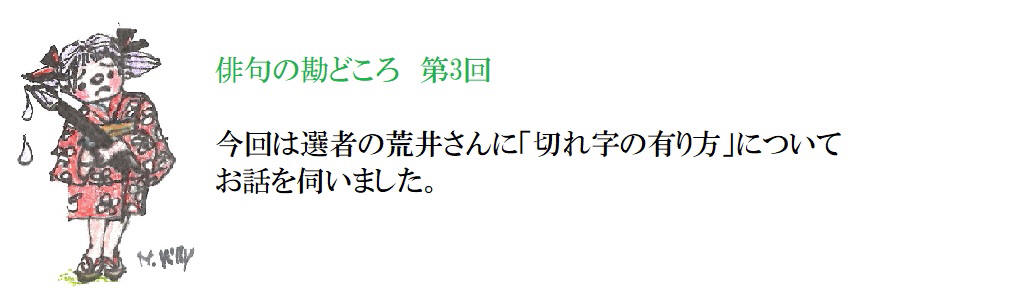
切れ字のあり方
俳句では昔から切れ字が使われてきた。切れ字はその前の語句の意味を強調するとともに、間をおいて、余韻を残したり、
リズムを整えたり、と、使いこなすと大きな表現力を味方につける手法だ。
現代俳句としては、強い切れ字として「や」「かな」「けり」がある。私は初心者の頃
その使い方が解らず足踏み状態で悩んでいた。しかし幸いなことに善き先輩に恵まれ、その指導のお陰で
その意を難なく呑み込むことが出来た。
そしてそれを自分なりにより上手く使い熟すことが出来るかと考えた挙げ句我ながら天晴れと思う案が浮かんだ。ちょっと惜しい気(笑)がするが 初心者の方々に此処で披露することにする。 文章を書くとき、誰もが句点と読点を打つと思う。
先ず 強い切れ字を「句点」に弱い切れ字を「読点」にそれをハマブン句会の入選句に記してみよう。
いわゆる、弱い切れ字というのは体言(名詞)や形容詞や動詞の終止形である。
案山子立つ乳房雲の真下かな。
小春日や。子を忘れつつ母の老いハーケンの音冴え冴えと刻みけり。
荒壁の鏝の返しや。青嵐一斉に蛙の合唱、母の里牛蛙、顔が無くなる大欠伸
青嵐、シェークスピアの壁の穴 と この様に必ず一句に一ヶ所 句読点が入らなければならない。
又二ヶ所に使うと「三段切れ」と言われ その句は捨てられてしまうことに。因みに三段切れになってしまった俳句を記すことにする。
庭の柿、部屋から主人、鴉番夏めくや。腹を見せたる蛙かな。(切れ字が二つ入っています)
朧月、家路へそぞろ歩きかな。
(最後に強い切れ字が来る場合、上五は切れない方がリズムがいいです)
勿論 切れ字が全く無くてはズルズルとした面白味の無い「だから何ですか?」
と問われる俳句になってしまうのである。
(荒井理沙)